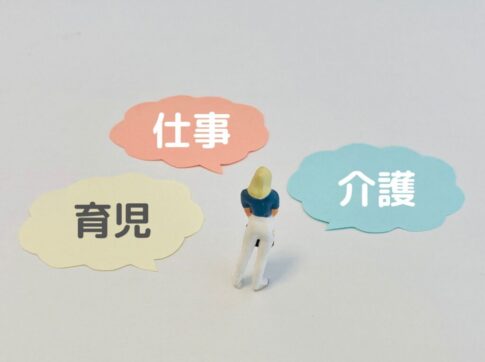こんな悩みはありませんか?退職をすることは、自分の大切な新しい未来への第一歩になるので悩みや不安がありますよね。「なるべく会社に迷惑をかけたくない」「できるだけ円満に退職したい」と悩んで退職することを先送りにしてしまうことも。
しかし、退職のタイミングを間違えてしまうと次のキャリアなどに影響が出るかもしれません。大切なのはタイミングを見極めて、計画的に行動をすること。この記事では、退職におすすめのタイミングを分かりやすく解説します。自分にとってベストな時期はいつなのか?どうすればスムーズに退職できるのか?これを読めば、あなたの悩みがきっと解消されるはずです。
最後まで読んで、ぜひ参考にしてください。
退職のタイミング
ここではさまざまな退職のタイミングを紹介します。自分の悩みや今自分がおかれている環境があると思いますので参考にしてください。
キャリアチェンジをしたい
キャリアチェンジをしたいと思ったときこそ、退職におすすめのタイミングです。
環境がリセットされることで新しいスタートを切れたり、新しい職に就くことでいろんなスキルや広い視野を手に入れるからです。
例えば接客業からWebデザイン職に転職したい場合、今の仕事を続けながら学習時間を確保するのは難しいこともあります。ほかにも事務職からカウンセラー職への転職などスキルや資格が求められる職種に移るケースでは、思い切って退職してから準備するのが効率的です。
キャリアチェンジを目指すなら、退職のタイミングを計画的にとることで、理想の職種に近づくチャンスが増えるのです。
結婚・出産

結婚や出産のタイミングは、退職を決断する良いタイミングです。
なぜなら、ライフスタイルが大きく変化するこの時期に、自分自身や家族の将来を見つめ直すきっかけとなり、新たな生活設計を立てやすいからです。
例えば、出産をきっかけに育児に専念したいという理由で退職した人は、心の余裕が生まれ子育てに集中できたという声が多くあります。また、結婚後にパートナーの転勤や引越しがある場合、柔軟に対応しやすくなるというメリットもあります。
結婚・出産という人生の転機は自分にとって最適な働き方や生活スタイルを見直す良いタイミングであり、退職のタイミングとしても良いでしょう。
職場環境や健康への影響

職場環境や自分の健康に影響がある場合退職するのがベストですが、まずは自分自身の体調を考えてください。
なぜなら、悪化した職場関係の中で精神的・身体的に限界を感じていても無理をして働き続ければ長期的に見て体調の回復が遅れる可能性があるからです。
例えば、職場でのパワハラや過度な残業など長く続くストレスで健康に害をおよぼす場合、まずは病院に相談して休養や休職を考えることが大切です。悪化した職場環境や体調のまま耐え続けることは健康やキャリアにとって大きなリスクとなるからです。
職場環境や健康に影響がある場合、無理に働き続ける必要はありません。改善が難しいと感じたときは、早めに退職を決めることが重要です。そうすることで、心身の健康を守りながら、キャリアの未来をより良い方向へ進めることができます。
退職の時期
ここからは退職の時期について詳しく解説します。タイミングが分かったら次は「いつ退職するのがベストか?」5つ厳選したので参考にしてください。
王道な転職活動を終えて次の職場が決まってから
転職活動を終えて次の職場が決まってから退職するのもおすすめです。
なぜなら在職中に転職活動をすると収入が途切れず生活の安定を保てたり、焦らずに自分に合った職場を選べるからです。
退職してから転職活動を始めた場合、転職活動に集中はできますが在職していた収入が無くなってしますので貯金を切り崩しながら転職活動を続けることになります。その場合「早く職場を決めないと」という焦りから、あまり希望の条件に合わない会社に就職してしまったというケースがあります。
退職前に進めておくことで精神的にも経済的にも余裕をもった転職活動ができるでしょう。しかし、もし競合の同業他社(自分たちと同じようなビジネスをしている会社)に転職を考えている場合は競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)というものが発生します。
競業避止義務とは?
退職後に同じ業界でライバル会社に転職をしたり、競争することを避ける義務。
・在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼職など)を行なうことを禁止すること
・一般の企業において、従業員の退職後に競業他社への就職を禁ずることを定めた、就業規則や個々の誓約書等に含まれる特約(競業禁止特約ともいう)」
【Wikipedia「競業避止義務-労働法における競業避止義務」より一部引用】
転職をする際は、会社に入社したときに署名した誓約書や就業規則をきちんと確認してください。
求人の多い時期
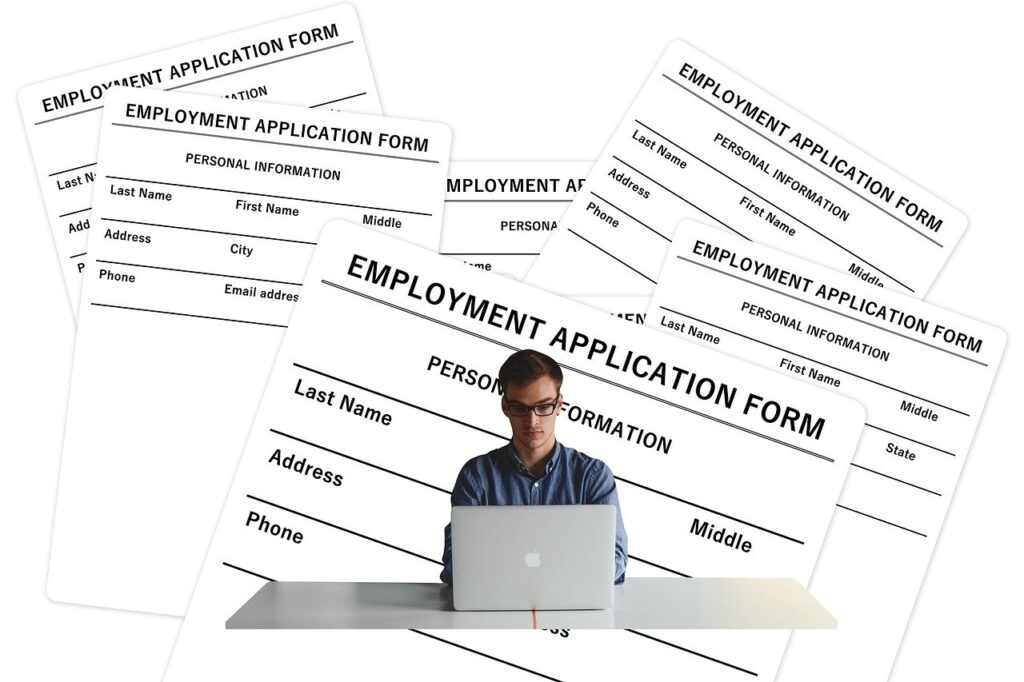
求人の多い時期に退職をするものおすすめです。
なぜかというと、求人の多い時期は選択肢も多く自分に合った職場を見つけやすくなり、また企業側も採用意欲が高いため内定までのスピードが早いパターンがあるからです。
例えば、3月〜4月や9月〜10月は年度や半期の切り替え時期で、企業が新しい人材を必要とするため求人数が増加します。このタイミングで退職・転職活動を始めると、希望条件に合う仕事が見つかりやすくなり、ブランク期間も短く抑えられます。
求人が多い時期に退職することで、より良い転職先と出会える可能性が高くなるため、計画的なタイミングでの退職をおすすめします。
円満退職しやすい仕事の閑散期
円満退職を希望であれば仕事の閑散期に退職することを強くおすすめします。
なぜならチームへの影響を最小限に抑えやすく、仕事のしっかりとした引継ぎをおこなえるからです。
- サービス業…年末年始が終わった1月~2月、夏休みが終わった後の9月
- イベント業…寒さや天気の影響の受けやすい1月~3月、9月~11月
閑散期だと同僚や上司も余裕をもって対応できますし、逆に繁忙期に退職を伝えてしまうと「こんな忙しい時に…」とネガティブな印象を持たれてしまいますし、引継ぎが不十分になるリスクがあります。
このような事から円満退職しやすい仕事の閑散期に退職することをおすすめします。
ボーナスの支給後や昇進後のタイミングで

ボーナスの支給後や昇進後のタイミングで退職するのも一つのプランです。
- ボーナス支給後に退職…次の就職活動に経済的余裕が生まれる。
- 昇進後に退職…自分の価値を認められた状態で有利に次のステップに進める
ボーナスの支給後に退職した場合、例えば退職後の引っ越し費用や新生活の準備費用として活用できるでしょう。
昇進後に退職した場合、例えば昇進後に得られる新しい肩書や役職を持つことで、履歴書に載せる内容が充実し、転職先での評価や条件交渉に役立ちます。
ボーナスの支給後や昇進後に退職した場合、余裕をもって新しいキャリアへの準備をスムーズに進められると言えます。ただし、会社の就業規則の関係で退職のタイミングにとってはボーナスの支給がされない場合があるので勤めている会社の就業規則をきちんと確認しましょう。
何かプロジェクトを終わらせてから
もしなにか現在プロジェクトを任されているのであれば終わらせてから退職すると会社や顧客から信頼を得て、円満に退職することができます。
プロジェクトの完了は、責任を果たす上で欠かせない行動です。これにより、会社や同僚に良い印象を残し、後任者やチームへの負担を軽減できます。未完了のまま退職すると、業務の混乱が生じるだけでなく、関係悪化の原因になりかねません。
例えば、営業職で大口案件を担当している場合、契約成立まで取り組んで退職すれば、会社や顧客から信頼を得られます。一方、途中で放棄すると、会社に損失が発生するだけでなく、今後のキャリアにも悪影響をおよぼすかもしれません。
プロジェクト完了後に退職することで、責任感ある行動として周囲から尊敬され、次のキャリアへのいいスタートが切れる可能性が高まります。
伝えるタイミング
ここからは次のステップで「いつ伝えるか?」です。ここでは一般的な例や「なるべく円満に退職を」と考えている方もいると思いますので参考にしてください。
一般的には1~2カ月前
退職を伝えるタイミングとして一般的なのは退職日から逆算して1カ月~2カ月前と言われています。
なぜなら充分な期間をもって通知をすれば会社側も余裕をもって人員配置や後任者の選定に時間をかけることができるからです。
例えば自分の仕事があった場合、後任者を選任してそこから業務内容などを説明するのに時間が必要になります。きちんと期間を設けて引継ぎをすることで未完了の義務が滞る心配もなく会社側もスムーズに運営が続けられます。
退職を伝えるタイミングを1~2カ月前にすることで会社への配慮をしつつスムーズに退職できるでしょう。
円満退職であれば2~3カ月前
1~2カ月前に退職を伝えるもの充分ですがさらに余裕をもって2~3カ月前に退職を伝えると円満に退職できます。
なぜなら2~3カ月前に伝えることで、さらに余裕を持った対応が可能になり、会社や同僚への配慮を最大化できるからです。
1~2カ月前の通知であれば、現在の業務が引き継ぐ期間としては十分です。しかし、例えば長期プロジェクトや専門スキルを必要とする業務の場合、2~3カ月前に通知すれば後任者がその業務を学ぶ時間を確保できます。また、より丁寧な引き継ぎによって会社側の混乱を避けることができます。
このようにさらに余裕をもって対応すればより良い印象で退職が可能です。
会社の就業規則に従って
ここまでで退職のタイミングを伝えてきましたが基本は会社の就業規則に従うことがいいでしょう。
なぜなら会社ごとに就業規則が違うため、「一般的には1カ月前と書いてあるけど自分の会社の就業規則には3カ月前だった」というケースもあるからです。
例えば就業規則に従わないで退職をした場合法的なトラブルや退職時の関係悪化につながる恐れがあります。会社の就業規則に従いきちんと退職手続きをとればトラブルも防げます。
基本的に会社の就業規則をきちんと読んで就業規則に従い退職の手続きをとるといいでしょう。
誰に伝えるべきか
退職を決めてから「まず誰に伝えるべきか?」会社では以下の方に伝えるようにしましょう。
直属の上司

退職を決めてから最初に伝える人は必ず直属の上司に報告しましょう。退職の相談 などはチームメンバーや同僚でもできますが報告は必ず直属の上司にしてください。
なぜなら退職の承認の遅れや引継ぎなどのトラブルを避けるためと直属の上司より先に他の方から退職を知った場合、直属の上司もいい気はしないからです。
例えば直属の上司であればあなたの業務状況も把握しています。最初に退職の報告をすることで引継ぎなどの手続きがスムーズにおこなえるでしょう。逆に他の同僚から直属の上司に知った場合、関係がぎくしゃくする可能性がありますし最悪の場合「なぜ直属の私に最初に報告しないのか」と退職の承認も遅れてしまう恐れがあります。
このようにスムーズに退職の手続きをおこなえるよう直属の上司に伝えましょう。
チームメンバーや同僚
直属の上司に退職を報告したら次はチームメンバーや同僚に伝えるといいでしょう。
なぜならチームメンバーや同僚は共に仕事をする仲間です。自分の退職を伝えればスムーズに引継ぎもできるからです。
例えば退職することが決まり、チームメンバーや同僚は今後の作業分担を計画しやすくなります。また退職までの期間まで引継ぎをスムーズに進めることができるでしょう。
チームメンバーや同僚に伝えることも大切です。しかし混乱を予想される場合、直属の上司に「チームメンバーや同僚に伝えていいのか」や「どのように伝えた方がいいのか」を確認しておきましょう。
取引先
取引先にも退職の挨拶をすることで、信頼関係を築きながら円満に退職ができ、次のキャリアでもいい印象を活かすことができます。
なぜなら突然の退職で混乱を防ぎ、スムーズな引継ぎができると共に退職時に挨拶をすることで長期的な信頼関係も築けるからです。
例えば、退職前に取引先へ挨拶をし、「お世話になりました」と感謝を伝えることで、退職後も良い関係が続きやすくなります。転職先で取引先とのつながりが活かされる場面もあるでしょう。一方で、挨拶をせずに退職すると「不誠実」と受け取られ、信頼を損ねる恐れがあります。
取引先に挨拶をすることで、これまで築いた信頼を守り、退職後のキャリアにもプラスの影響をもたらすことができます。ただし、挨拶の仕方など会社によって違うので、挨拶をする前に上司に確認をとっておいた方が安全でしょう。
まとめ
ここまでで退職の「タイミング」「時期」「誰に伝えるべきか」を紹介していきました。
退職は一つの節目であり新たな人生の第一歩の始まりです。
退職は不安がともなうものですが、それ以上に新しい可能性への扉を開くチャンスです。「自分にとってベストなタイミングはいつか?」を考え、計画的に行動しましょう。
私たちがあなたを徹底的にサポートさせていただきます。
退職の手続きのしかたや新しい職場探しに困っているときは一緒にピッタリな職場を探していきましょう。
ぜひ気軽にお声がけください。お待ちしております。